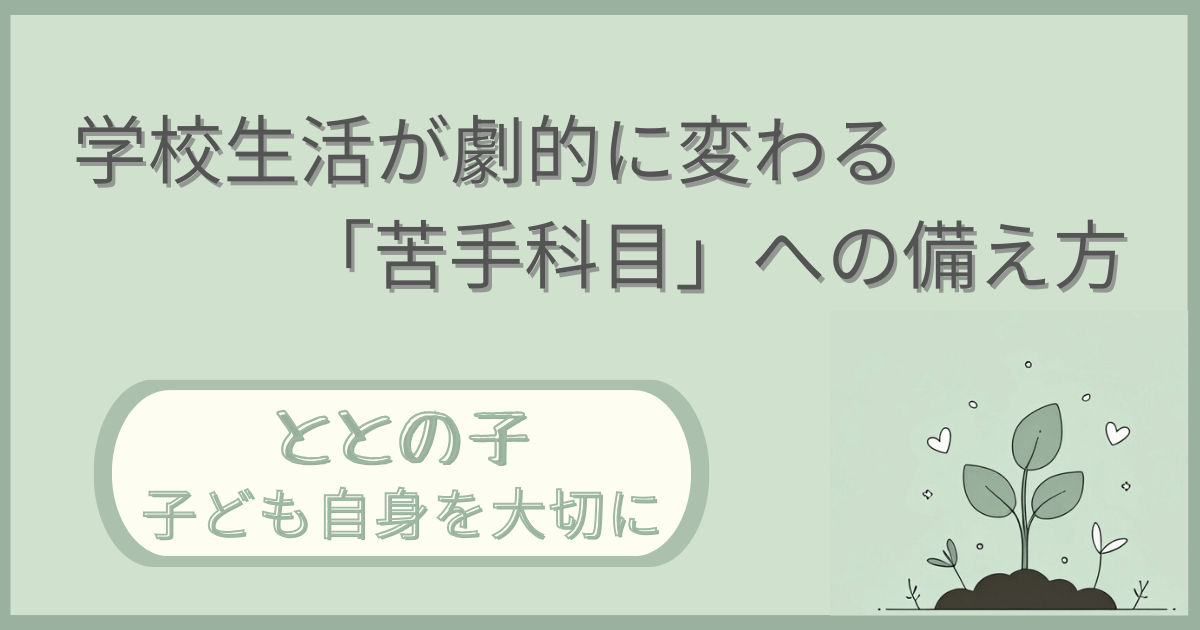子どもが勉強でつまずくと、多くの親はすぐに塾や家庭教師を思い浮かべます。「苦手を補う」「自信をつける」ために、勉強には投資するのが当たり前になっています。
では、体育や音楽、美術などの実技教科が苦手なときはどうでしょう?
多くの場合は、親は「気にもしていない」もしくは、「仕方がない」とあきらめていることが多いのではないでしょうか?
でも、勉強だけではなくどの教科であっても苦手教科があるだけで学校生活が苦痛になってしまうシーンが多いはずです。
この記事では、苦手教科全般に使えるサポート法と、その効果をわかりやすくご紹介します。
1. 苦手教科が学校生活をつらくする本当の理由
苦手な授業は、その時間だけでなく、学校生活全体を重くします。特につらいのは「周囲と比べられる瞬間」です。
- 体育なら、ほかの子は簡単にできることを自分だけ何度も繰り返し練習させられる。
- 音楽なら、みんなの前で歌ったときに笑われる。
- 美術なら、作品を並べたときに差が目立つ。
- 勉強なら、授業中にノートが追いつかず、答えられない。
こうした状況が続くと「自分はできない」という自己認識が強まり、自己肯定感が大きく下がります。やがて学校そのものが苦痛な場所になってしまうこともあります。
わたし自身も小学生の頃、体育がとても苦手でした。鉄棒やマット運動で「できるまでやめられない」状況が何度もあり、できた子が座って見ている中で一人残されるのは、とてもつらい時間でした。「どうして自分だけできないんだろう」という気持ちばかりが大きくなっていったのを今でも覚えています。
こうした経験は体育だけでなく、音楽や美術、勉強でも起こり得ます。つまり「集団の中で自分だけできない状態」が苦痛の本質なのです。
2. 苦手克服の第一歩|放置せず“嫌じゃない”に変える発想転換
「勉強についていけない」ことより、「実技教科で周囲からおいていかれる」ことを軽視していませんか?「苦手なんだから仕方がない」という考え方から、少しだけ発想を変えてみましょう。
苦手なことを習い事として取り組むことを嫌がるお子さんは多いと思います。嫌いなことをやりたがらないのは当然です。親としては、無理にやらせなくてもいいと思ってしまいますよね。
しかし、子どもが嫌がるのは、集団の中で自分ができないことを突きつけられ、学校と同じつらさを繰り返すことが原因かもしれません。
苦手対策の習い事で大切なのは、「環境を選べる」という発想です。比較やプレッシャーのない個別指導や少人数レッスンなど、その子に合った場所を見つけてあげることが、苦手克服の第一歩です。
3. 勉強以外でも使える苦手克服の方法|体育や音楽の少人数・個別指導
体育、音楽、美術などを子どものお稽古ごとにする場合、ビアノなどの楽器レッスン以外は個人レッスンを思い浮かべる人は少ないと思います。
でも、勉強に塾や家庭教師があるように、体育や音楽、美術などの実技教科にも個別で教わる場があります。
- 体育 → 体育家庭教師、個別スポーツ指導
- 音楽 → 個別ボーカル
- 美術 → 個別絵画・造形指導
マンツーマンで基礎から教えてもらうことで、短期間で苦手が改善する場合があります。何より、「できるようになる」という成功体験が、子どもの自信を回復させます。
4. 苦手が減ると学校生活がラクになる理由
すべての教科を「大好き」にすることは難しいかもしれません。でも、苦手な時間を「嫌じゃない」に変えるだけで、学校生活は格段にラクになります。
- 授業中の緊張や不安が減る
- 放課後や休日のエネルギーを、好きなことに使える
- 周りと比べるストレスが減り、自分のペースで楽しめるようになる
子どもが「学校は全部楽しい」と言えなくても、「嫌な時間が減った」こと自体が、毎日の笑顔につながるのです。
5. 自己肯定感を守るための親のサポート法
子どもの苦手に向き合うことは、親にとっても簡単なことではありません。しかし、親のちょっとした関わり方が、子どもの気持ちを大きく変えるきっかけになります
苦手を「我慢」させない
苦手な教科の授業は、苦痛な時間が過ぎ去るのを「我慢」するものではありません。
もし、お子さんがつらさを我慢しているように感じたら、気づいて寄り添ってあげてください。
- 感情に共感する
- 「嫌だよね、しんどいよね」と、まず子どもの気持ちをそのまま受け止めましょう。つらい気持ちに寄り添うだけで、子どもは「自分はひとりじゃない」と感じ、安心できます。
- 目標は“好き”より“嫌じゃない”
- 無理に得意にさせようとすると、親も子もプレッシャーを感じてしまいます。目標は、「嫌な時間」を「嫌じゃない時間」に変えることです。
「できない自分」を肯定する
- 得意・不得意はあって当たり前
- そもそも、すべてを完璧にできる人はいません。人にはそれぞれ、得意なことと苦手なことがあります。「できないこと」がある自分を否定する必要はまったくありません。
- 「伸びしろ」と捉える
- 「できない」ことはネガティブなことではなく、これから成長できる「伸びしろ」があるということです。その子の個性やペースを認め、小さな変化を一緒に喜んであげましょう。
- 頑張りではなく、向き合った姿勢を認める
- 結果がすぐに出なくても、嫌なことにも逃げずに挑戦したこと、最後まで取り組んだ姿勢をしっかり褒めてあげてください。その真面目さや粘り強さこそが、子どもの大きな自信につながります。
具体的な解決策を探す
苦手な授業の苦痛な時間を我慢させるのではなく、お子さんに合った解決策を一緒に探してあげましょう。
勉強に塾や家庭教師があるように、体育や音楽などの実技教科にも専門のサポートがあります。お子さんの性格に合わせて選びましょう。
- 個別指導
- 「できない自分を人に見られるのが苦手」なお子さんには、個別指導が向いています。人目を気にせず、自分のペースで取り組めるため、気持ちが楽になります。
- 友達と一緒
- 「苦手なことでも大好きな友達となら頑張れる」というお子さんには、友達と一緒に受けられる集団レッスンの方が向いている場合もあります。
お子さんが「苦手だけど授業は苦痛じゃないよ」と言っても、言葉通りに受け取らないことも大切です。うまく気持ちを伝えられないだけ、あるいは強がっているだけかもしれません。子どもの気持ちに寄り添いながら、学校生活がしんどくないか気にかけてあげてください。
まとめ
学校生活のつらさは、「苦手そのもの」よりも「苦手な状況に長くさらされること」から生まれます。その時間を減らすためには、環境を選び、苦手を「嫌じゃない」レベルにしていくことがカギです。
その一歩目として、子どもに合った学びの場を一緒に探してみましょう。
実技科目の中でも体育が苦手なお子さま向けの記事はこちらから
この記事を読んでくださり、ありがとうございます。
思春期の子どもを持つ50代母です。
かつて仕事で子育てセミナーを企画運営する中で、専門家の知見や多くの親の悩みに触れてきました。
自身の経験とプロの視点を踏まえ、親の心のゆとりと、子どもの主体性を尊重する姿勢が大切だと確信。
このブログでは、ずぼらな面もあるわたしが、無理せずラクに心地よく暮らすヒント、完璧じゃなくてもいい工夫を発信することで、あなたの子育てを優しく”ととのえる”お手伝いをしたいと考えています。