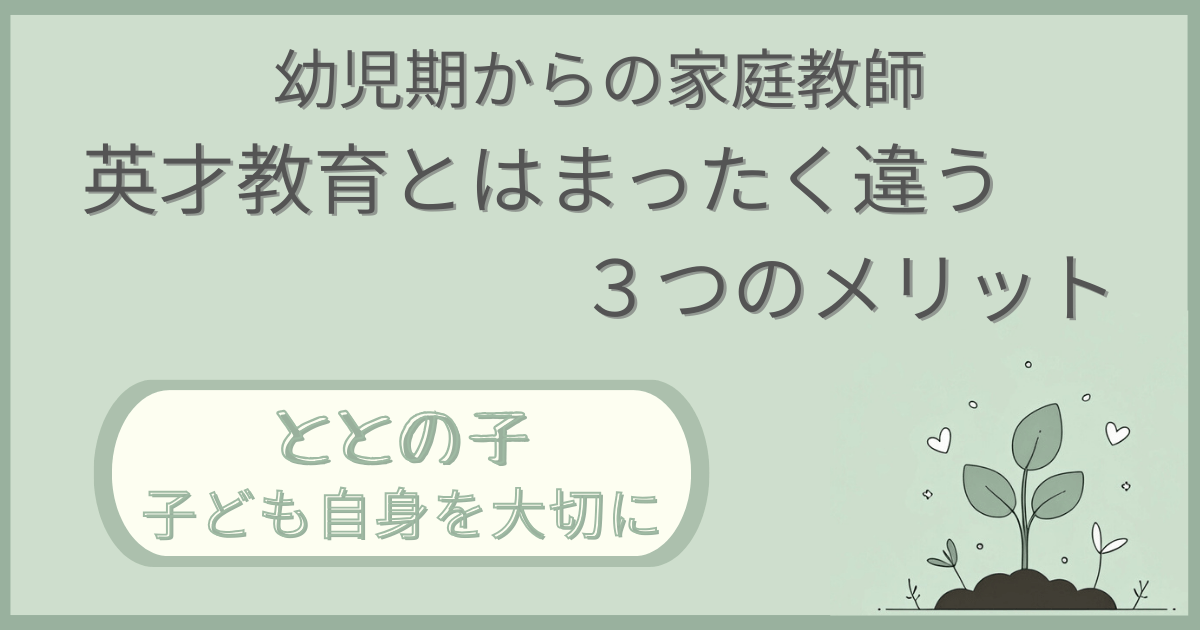お子さんの習い事といえば、英語、ピアノ、プログラミングなど多彩です。その中で「家庭教師」と聞くと、幼稚園・保育園のうちから?と驚かれる方も少なくありません。
「まだ早いのでは?」「英才教育を狙っている人がすることでは?」と思う方もいるでしょう。
一方で、多くの保護者が「小学校入学前に学習習慣の基礎をつけたい」と願いながら、「子どもの個性を大切にしたい」という思いの間で揺れています。
幼児期に家庭教師は早い?結論:勉強嫌いを防ぐ“きっかけ”になる
未就学児にとって、小学校で始まる勉強は避けて通れません。最初は楽しくても、つまずきや失敗から「勉強=つらい」と感じてしまうことがあります。
心理学研究(Bandura, A. Self-efficacy: The exercise of control, 1997)でも、幼少期に「できた!」「楽しい!」という経験を重ねることが、将来の学習意欲や自己効力感(=自分ならできるという感覚)につながるとされています。
だからこそ、「勉強=楽しい」という気持ちを小学校前から育むことが大切なのです。
幼児期から家庭教師を利用する3つのメリット
1. 学校生活へのスムーズな準備
ひらがなや数字に自然と触れ、学びを遊びとして楽しめるようになります。
好奇心を大切にすることで「勉強って面白い!」という感覚を早くから持てるのが大きな強みです。
2. 保護者の負担軽減
親が直接教えると感情的になりがちです。第三者である家庭教師が関わることで、親子関係が穏やかになり、家庭が安心できる学びの場に変わります。また、その時間を家事や自分の時間に充てられるのも魅力です。
3. 子どもの「学びたい!」を引き出す
家庭教師は一人ひとりのペースに合わせて柔軟に個別指導します。絵本のキャラクターから文字を学んだり、おもちゃを数えながら数字を覚えたりと、興味関心を探究の出発点にできるのが大きな特徴です。
幼児に塾と家庭教師、どっちがいい?
「塾でもいいのでは?」と考える方も多いはず。両者には次のような違いがあります。
送迎の負担
- 塾
- 必ず送迎が必要です。共働きや兄弟のいる家庭では大きな負担になります。私自身、塾の授業が60分だと、家に帰るには早すぎるし、かといって買い物やお茶で時間を潰すちょうどいい場所もなく、「ただ時間を待っているだけ」という感覚になった経験があります。正直、この送迎時間が一番もったいないと感じました。
- 家庭教師
- 自宅に来てもらえるため、移動時間がゼロになります。送迎の時間がなくなることで、家事や自分の時間を有効活用できます。
学習の進め方
- 塾
- カリキュラムに沿って進むため、「ひらがなが書ける」「たしざんができる」といった成果を優先します。
- 家庭教師
- 個別対応が可能。「昆虫の名前をきっかけに文字を覚える」など、子どもの興味に寄り添えます。
教育の方向性
- 塾
- 基礎学力を系統立てて固めやすく「英才教育」向きです。
- 家庭教師
- 遊びや探究と結びつけやすく、自然に「勉強は楽しい」と実感できます。
結論
どちらが良い悪いではなく、幼児期に“学びの楽しさ”と“保護者の負担軽減”を両立させたいなら家庭教師がいいと感じています。
幼児の家庭教師の費用は?―実はシッターと大差なし
「家庭教師=高額」というイメージがありますが、実際にはベビーシッターと大きく変わりません。
厚生労働省のデータでは、ベビーシッターの平均料金は次の通りです。
厚生労働省2019年「ベビーシッター事業の現状と課題」
- 会員料金(基本時間):1,795円
- ビジター料金(基本時間):2,244円
- 地域差あり(基本時間:東京2,064円、東京以外1,678円)
家庭教師も、1時間あたり約2,000円+登録料・会費から始められるケースがあり、「学習サポート+シッター機能」と考えるとコスパは高いといえます。特に小学生のお兄ちゃん・お姉ちゃんがいる場合は、同時指導割があるので一緒に指導を受けるとかなりお得です。
※詳しい料金相場やサービス比較は次回記事で解説します。
まとめ:幼児期からの家庭教師は「英才教育」ではなく「人生の羅針盤」
小学校は子どもにとって初めての社会です。ここで「勉強に前向きな姿勢」を持てるかどうかは、充実した学校生活とその後の人生に大きく影響します。
家庭教師は、無理な先取りを強いるものではなく、子どもに「勉強って楽しい!」という感覚を育む伴走者です。
お子さんに「人生の羅針盤」を渡すつもりで、幼少期からの家庭教師を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
この記事を読んでくださり、ありがとうございます。
思春期の子どもを持つ50代母です。
かつて仕事で子育てセミナーを企画運営する中で、専門家の知見や多くの親の悩みに触れてきました。
自身の経験とプロの視点を踏まえ、親の心のゆとりと、子どもの主体性を尊重する姿勢が大切だと確信。
このブログでは、ずぼらな面もあるわたしが、無理せずラクに心地よく暮らすヒント、完璧じゃなくてもいい工夫を発信することで、あなたの子育てを優しく”ととのえる”お手伝いをしたいと考えています。