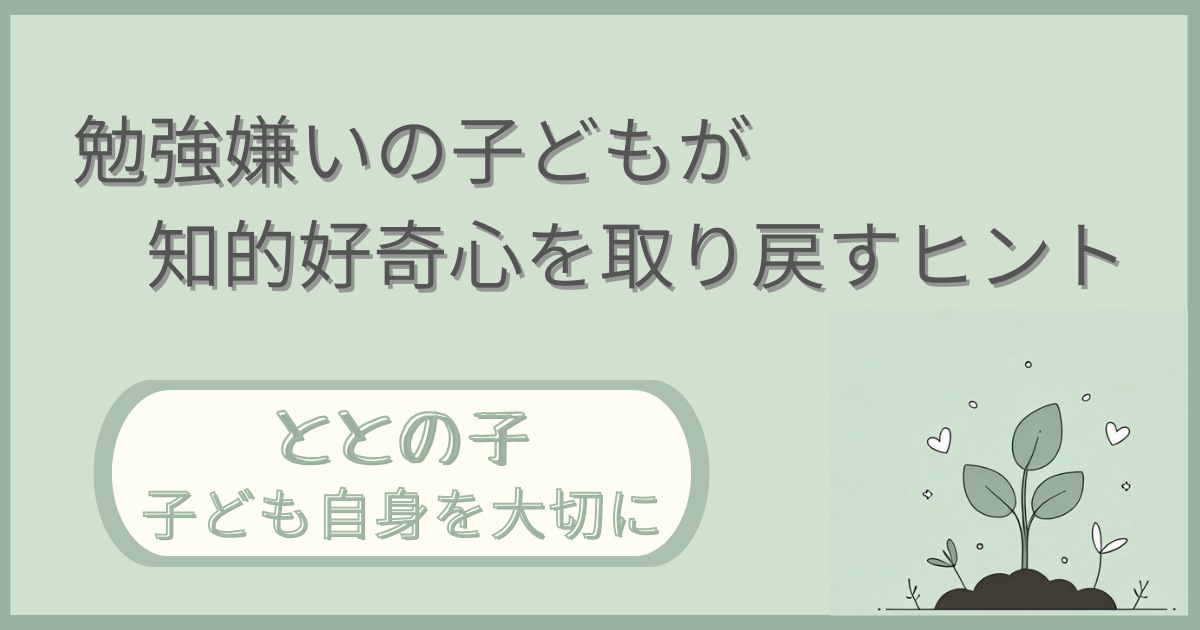子どもが、小学校高学年のときに、こんな話をしてくれました。
「勉強はできるのに、勉強が嫌いな友達がいるんだ。今まで、勉強が嫌いな子は勉強が苦手な子ばかりだったからびっくりした…」
「できるなら、きっと楽しいはず」と純粋に思っていた子どものにとって、その子の存在は大きな驚きだったようです。そしてその友達は、こう言ったそうです。「だって、点を取らなきゃ怒られるからやっているんだもん」と。
実はこの「嫌いになる理由」、成績の高い子だけでなく、勉強が苦手な子にも共通しています。
この記事では、成績の良し悪しに関わらず「勉強が嫌いになる」背景を整理し、子どもが本来持っている「知ることの楽しさ」を取り戻すための入り口をご紹介します。
「わかった!」の喜びは、成績に関係なく誰でも味わえる
勉強が「楽しい」と感じる瞬間は、テストで良い点を取ったときだけではありません。
それは、昨日までわからなかったことが、今日になって「わかった!」と腑に落ちた瞬間。解けなかった問題が、自分の力で「できた!」と感じた瞬間です。
この「わかった」という喜びは、客観的な成績や点数とは関係なく、すべての子どもが味わえる、学びの最大の魅力です。
子どもの心を「やらされている」という義務感から解放し、「自分でやってみよう」という気持ちを引き出すことができれば、勉強は楽しいものに変わっていきます。その鍵を握るのは、親の関わり方です。
楽しかったはずの「知る喜び」が「義務」に変わるとき
子どもの頃、誰もが「なぜ、空は青いの?」「どうして鳥は飛べるの?」と、尽きることのない疑問で大人を困らせた経験があるのではないでしょうか。
しかし、小学校に上がり、勉強が始まると、この「なぜ?」という純粋な知的好奇心が、少しずつ変化していきます。
テストの点数や順位、そして親や先生からの評価。勉強はいつしか、自分の好奇心を満たすためのものではなく、他者からの評価を得るための「義務」になってしまうことがあります。
「宿題、ちゃんとやったの?」「どうしてこんな点数なの?」
こうした言葉がけが、知る喜びよりも「やらされている」という気持ちを強くしてしまい、勉強そのものを嫌いなものに変えてしまう可能性があるのです。
ゲームは楽しいのに、なぜ勉強は嫌いなの?「点数」の持つ意味が違う理由
子どもたちは、ゲームの点数を上げるために、熱中して何度も挑戦します。失敗しても「次こそは!」と楽しんで頑張ることができます。
一方で、勉強で良い点数を取っているお子さんでも、なぜか勉強を嫌いになってしまうことがあります。
それは、ゲームと勉強の「点数」が持つ意味が根本的に違うからです。
- ゲームの点数
- 「挑戦」と「成長」の記録: 失敗しても「次に活かせるヒント」になります。何度でもやり直しがきき、試行錯誤するプロセスそのものが楽しみになります。
- 自分のためにある: 自分の腕を磨き、高みを目指すための個人的な指標です。
- 勉強の点数
- 「能力」と「評価」の証明: 高得点を取ることが当たり前になり、「失敗してはいけない」というプレッシャーを生むことがあります。
- 他者のためにある: 親や先生、そして社会からの評価を気にするあまり、子どもの心の負担になることがあります。
このように、ゲームの点数が「自分のための挑戦の記録」であるのに対し、勉強の点数は「高評価を維持するための証明」になってしまうことで、子どもは純粋に楽しむことが難しくなってしまうのです。
「好き」がなければ伸びは止まる
成績が良いお子さんでも、勉強が嫌いなままでは、いつか限界が来てしまいます。
勉強に対する「嫌い」という感情は、以下のような点で、お子さんの長期的な成長にマイナスに働いてしまう可能性があります。
- 自ら学ぶ意欲がなくなる
- 嫌いなことは、言われなければやりません。将来、学校や塾の枠を超えて、新しい知識を自ら学ぶ機会を失ってしまいます。
- 困難に立ち向かう力が育たない
- 勉強は、学年が上がるにつれて難しくなります。嫌いなことでは、壁にぶつかったときに「もういいや」と諦めてしまいやすくなります。
- 得意な分野が活かせない
- 苦手な分野を克服するだけでなく、本来「好き」であるはずの得意な分野でさえ、「嫌いな勉強」というくくりで捉えてしまい、その楽しさを十分に追求できなくなってしまいます。
本当に大切なのは、与えられた知識をこなす力だけでなく、自ら学び続ける力です。
解決の鍵は「子どもの主体性を尊重する」こと
では、どうすればこの状況を乗り越えられるのでしょうか? その鍵となるのが、子どもの主体性を尊重する関わり方です。
この関わり方は、成績の良し悪しや得意・不得意に関わらず、すべての子どもが持つ「知りたい」という気持ちを引き出し、自ら学ぶ力を育む上で非常に効果的です。
子どもの主体性を引き出すための具体的なヒントをいくつかご紹介します。
- 「いつ、何をやるか」を子どもに決めさせる
- 「やらされている」という感覚を減らし、「自分で決めた」という当事者意識を持たせることができます。
- 「どうすればできるようになるか」を一緒に考える
- 難しい問題に直面したとき、解決策を一緒に探してみましょう。自分で課題を解決するプロセスを体験することで、学びの楽しさを再び見つけることができます。
お子さんの「嫌い」というサインは、成長のチャンスでもあります。この機会に、一緒に「好き」を育んでみませんか?
子どもの主体性を尊重した関わり方のヒントをさらに知りたい方へ。
子どもの主体性を尊重するかかわり方の一つをご紹介しています。
→ 記事:今日の心づもりは?──子どもの主体性と親の心の余裕を守る“魔法のことば”
子どもの「苦手教科」や勉強嫌いが気になる方へ。
勉強だけでない体育・音楽・美術などの実技教科に対して苦手を克服する秘訣と自己肯定感について解説ています。
→ 記事:子どもの学校生活が劇的に変わる秘訣:「苦手教科」への備え方
「勉強についていけない」「勉強が嫌い」―そんな悩みを解消して学校生活を楽しむための勉強サポート方法を紹介しています。
この記事を読んでくださり、ありがとうございます。
思春期の子どもを持つ50代母です。
かつて仕事で子育てセミナーを企画運営する中で、専門家の知見や多くの親の悩みに触れてきました。
自身の経験とプロの視点を踏まえ、親の心のゆとりと、子どもの主体性を尊重する姿勢が大切だと確信。
このブログでは、ずぼらな面もあるわたしが、無理せずラクに心地よく暮らすヒント、完璧じゃなくてもいい工夫を発信することで、あなたの子育てを優しく”ととのえる”お手伝いをしたいと考えています。