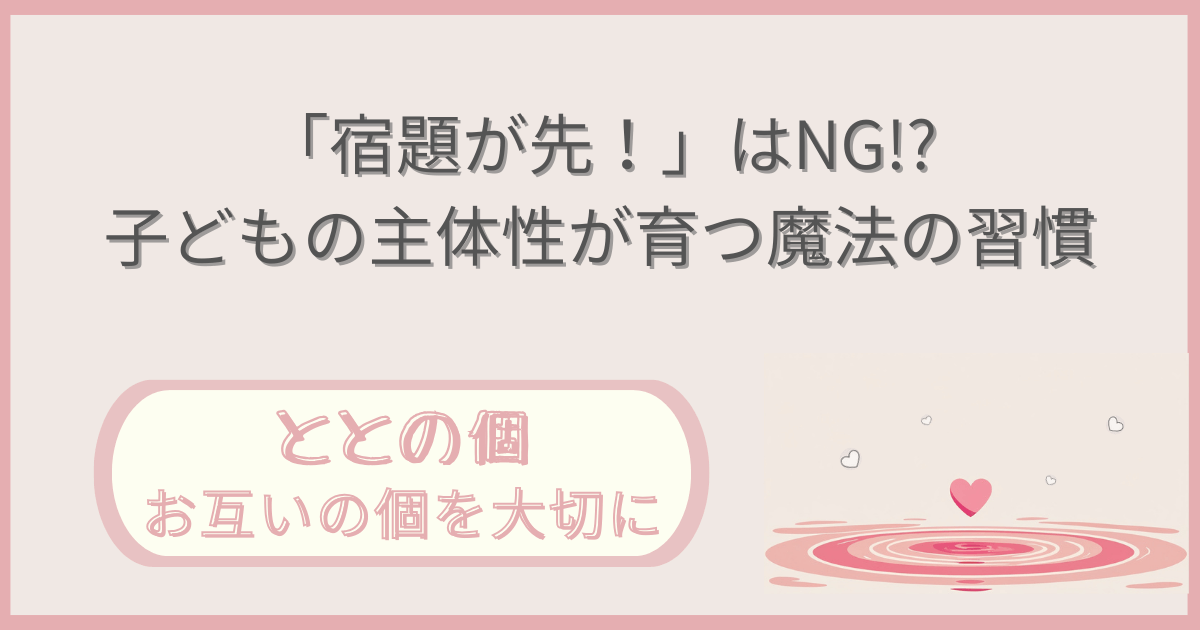「早く宿題しなさい!」この一言で、せっかくの笑顔が消えてしまう……そんな経験はありませんか?やるべきことを後回しにしない習慣は大切。でも、その言葉が親子バトルの火種になったり、子どもの「自分で考える力」を奪ったりするとしたら?
実は、わが子は家で宿題をいっさいしません。ある日、子どもが「家では楽しいことだけをしたい」と言ったんです。この言葉をきっかけに、「宿題は家でやるもの」という思い込みを捨ててみたところ、信じられないような変化が起こったのです。
子どもが主体的に決める宿題スケジュール:わが家の場合
家で宿題をしない、けど宿題はちゃんと提出いけない。その一見両立不可能なこと、実はとても簡単に解決可能でした。わが子は宿題を学校で終礼前の空き時間や放課後、友達と協力しながら済ませてきます。もし学校で終わらなければ、翌朝早く登校してやるというスタイルです。家では全く勉強しなくなりました(中学校になってからは、さすがに家で勉強する姿を時々見かけます(笑))。
この方法を始めた当初は、学校で済ませてこなかった日には、「明日寝坊したらどうするの?」「朝の時間で終わる内容なのかな?」と不安でいっぱいでした。もしかしたら、実際に宿題が間に合わなかった日があったかもしれません。わたしには全く勉強している姿が見えないので、ちゃんと宿題を提出したのか確認したくてたまりませんでした。でも、しつこく確認をすることは、「宿題しなさい」といっているのと同じことになってしまう。学校から連絡が来るまでは、黙って見守ろうと腹をくくりました。すると、子どもは自分で決めたことだからと、責任感を持って宿題に取り組むようになったのです。
わが子が家で宿題をしないように、お子さまにとっても自分の中で最適な「宿題をやる時間」がきっとあります。
宿題の時間を決めなくてもいい魔法の習慣
いつ宿題をするか事前に決めていなくても大丈夫です。
「宿題はいつやるの?」と管理するのではなく、以前の記事でご紹介した魔法の言葉を使ってみてください。
毎日帰宅したときに一言
「今日の心づもりは?」
これだけで十分です。
そして、お子さまの「心づもり」を黙って見守ってあげてください。お子さまは子どもは「自分で考えた計画を尊重してもらえた」と感じ、親子の信頼関係が深まります。
魔法の言葉「今日の心づもりは?」とはどういうものか気になる方はこちらの記事をどうぞ
「やらされる勉強」から「自分からやる勉強」へ
心理学でわかる「主体性が育つ理由」
心理学の研究(自己決定理論, Deci & Ryan)によると、人が意欲をもって行動するには次の3つの欲求が満たされることが大切だとされています。
- 自律性(autonomy):自分で選びたい
- 有能感(competence):できる!という手ごたえを感じたい
- 関係性(relatedness):信頼され、つながりを感じたい
「宿題をいつ・どこでやるか」を子ども自身に委ねることは、この“自律性”を満たすことにつながります。自分で決めた計画が親に認められ、計画通り宿題をこなすことで、自分はちゃんとできるという手ごたえ=有能感が高まります。さらに、親が見守っていて必要なときだけサポートすることで「関係性」が育ちます。結果として、子どもは「やらされる勉強」から「自分からやる勉強」へとシフトしていくのです。
親の役割は「管理」から「応援」へ
子どもの主体性を引き出すには、親が「管理する人」から「見守る応援者」へと役割を変えることが重要です。
- 宿題の様子をじっと見守る
- 困っていたら「どうしたの?」と寄り添う
- 失敗しても「次にどうすればいいか」を一緒に考える
もちろん、中には「早く宿題を終わらせて、すっきりした気持ちで遊びたい!」というタイプのお子さまもいます。その場合は“先に宿題を済ませる”方が安心につながります。大事なのは、親が一方的に決めることではなく、子ども自身が自分に合ったやり方を選べることです。
完璧な子育てマニュアルはありません。大切なのは、その子の気持ちに耳を傾けながら、一緒にやり方を探していくことです。
今日からできる実践チェックリスト
- 帰宅時に「今日の心づもりは?」と聞く
- 宿題のやり方やタイミングは子どもに任せる
- 失敗しても叱らず、「次はどうしよう?」と問いかける
- 見守りながら、必要なときだけサポートする
「ただいま!」「おかえり」の大切な時間。お子さまの顔に、笑顔が広がる毎日を大切にしていきましょう。
勉強嫌いの子どもに対する子育てのヒントを知りたい方へ。
勉強嫌いの子が学校生活を楽しむための勉強サポート法をまとめています。
→ 記事:勉強嫌いを克服!子どもが学校生活を楽しむための方法
「親が子どもの勉強をみる」」ことをやめて「子どもの応援者」になる3つのメリットについてお話しています。
→記事: 家庭学習でイライラしない方法:親が教えない選択が、親子の笑顔を守る
子どもの主体性を尊重することが「勉強って楽しい!」につながることについてお話しています。
→ 記事:「勉強って楽しい!:勉強嫌いの子どもが知的好奇心を取り戻すヒント」はこちらから」
子どもの主体性を尊重した関わり方のヒントを知りたい方へ。
子どもの主体性を尊重して、親子で「整った関係」を築くための魔法の言葉についてお話しています。
→ 記事:今日の心づもりは?──子どもの主体性と親の心の余裕を守る“魔法のことば”
この記事を読んでくださり、ありがとうございます。
思春期の子どもを持つ50代母です。
かつて仕事で子育てセミナーを企画運営する中で、専門家の知見や多くの親の悩みに触れてきました。
自身の経験とプロの視点を踏まえ、親の心のゆとりと、子どもの主体性を尊重する姿勢が大切だと確信。
このブログでは、ずぼらな面もあるわたしが、無理せずラクに心地よく暮らすヒント、完璧じゃなくてもいい工夫を発信することで、あなたの子育てを優しく”ととのえる”お手伝いをしたいと考えています。