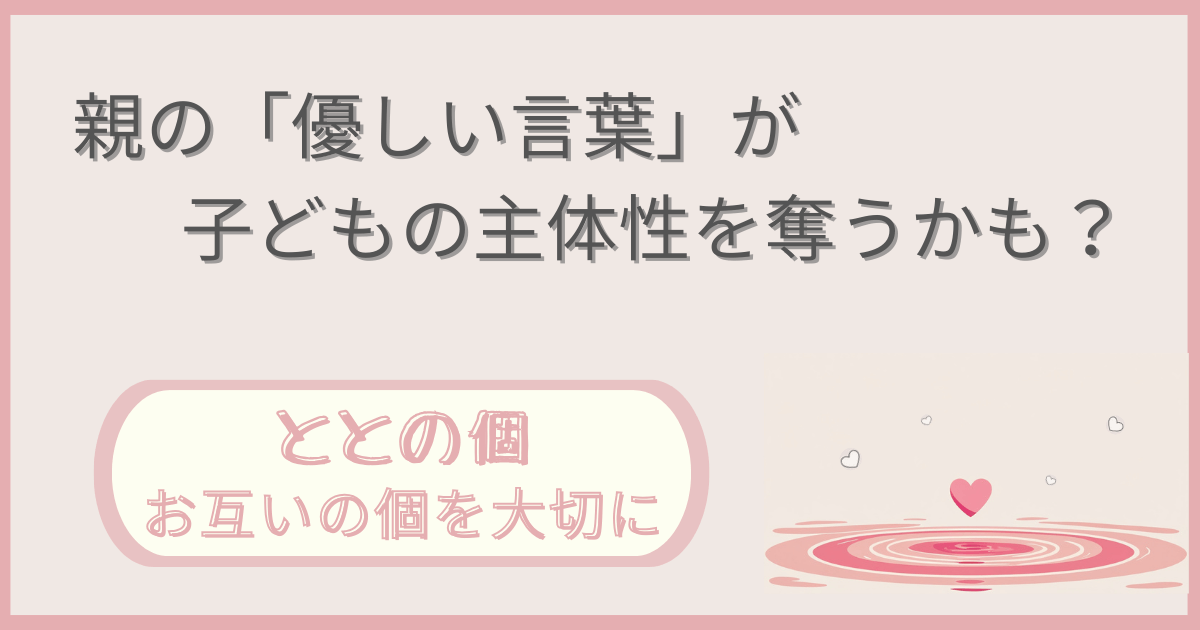「『あれ、まだやってないの?』『早く準備しなさい』。声をかけないと、子どもはなかなか動いてくれない…。そんな毎日に、少し疲れていませんか?」
子どもの自主性を尊重したいのに、放っておくと何も進まない。子どもの「やりたい!」という気持ちを大切にしたいのに、結局親がリードしないと何も始まらない…。そんなモヤモヤした気持ちを抱えていませんか?
でも、「『早くやりなさい!』『どうしてこんなことしたの!』。そんな言葉は言いたくない。子どもの主体性を尊重して『こうしてみる?』『一緒にやろうか?』と優しく声をかけている、そういうことはありませんか?
その想いは間違いなく子どもへの深い愛情です。
でも、なぜかその愛情深い言葉が、かえって子どもの「自分で動く力」を育ててくれないとしたら?
この記事では、親の優しい言葉に隠された意外な落とし穴と、子どもの主体性を本当に育むための方法についてお伝えします。
優しい言葉に潜む「「プレッシャー」と「依存」の落とし穴
あなたの優しい言葉には、子どもを無意識のうちに親への依存や期待に応えようとするプレッシャーに追い込む、2つの落とし穴が潜んでいます。
1. 「こうしてみようか?」の裏側にあるプレッシャー
大人でも、上司から「これ、やってみる?」と提案されたとき、すぐに「嫌です」とは言いにくいものです。
子どもにとって、親は絶対的な存在です。親子間には「力の不均衡」が存在するため、子どもは親の表情や声色から「親が喜ぶこと」を敏感に察知しています。
そのため、親が提示した選択肢を子どもが選んだとしても、それは本当に子どもが心から望んだ行動でしょうか?もしかしたら、「親をがっかりさせたくない」「親の期待に応えたい」という無意識の忖度が働いているのかもしれません。
2. 「一緒にやろう」の甘い罠
「「一緒にやろう」という声かけには、深い愛情があります。
ただしこれを繰り返すと、子どもが「困ったら親が助けてくれる」という依存心を持ちやすくなります。
子どもが自分で工夫し、試行錯誤する機会を奪っている可能性があるのです。
子どもの主体性を伸ばすために大切なこと
子どもの主体性を伸ばす鍵は、親の「頑張らない」という選択
「でも、放っておいたら何もしないから、信じて待つなんて無理!」そう感じるのは自然なことです。
けれど、優しい声かけが「親が声をかけてから動く子」という習慣を強めてしまうこともあります。
このサイクルを断ち切るカギは、親自身が「頑張らない」という選択をすることです。
「早くさせなきゃ」「ちゃんとさせなきゃ」と完璧を目指すほど、私たちは子どもをコントロールしようと焦ってしまいます。その焦りが、「優しい言葉」を子どもへのプレッシャーに変えてしまうのです。
だから、もう頑張らなくていいのです。
- 家事を少し手抜きする
- 子どもがグズグズしても完璧に対応せず、見守る
そうやって「頑張らない」ことで、心に小さな余裕が生まれます。その余裕こそが、子どもを「信じて見守る」という心のゆとりを生み出すのです。
親のゆとりが、子どもの自己肯定感を育む
親が「この子はきっと自分でできる」「失敗しても大丈夫」と見守る心のゆとりは必ず子どもに伝わります。親の信頼という安心感を背に、子どもは自分で挑戦し、試行錯誤を繰り返すことができるのです。
そして、その過程で、自分で見つけた解決策や、自分の力で成し遂げた成功体験こそが、子どもの「自分にはできる」という自己肯定感・自己効力感を育み、真の主体性へとつながります。
親子の時間を「解決」ではなく「楽しむ」に
もちろん、親子の時間を大切にすることは素晴らしいことです。
ただ、その時間を「課題を解決するため」ではなく「一緒に楽しむ時間」として過ごしてみませんか?
例えば、ゲームを一緒にしたり、公園で思い切り遊んだり。
「こうなってほしい」という期待を手放し、ただ楽しむ。
この経験が、子どもにとって何よりの安心感と自己肯定感につながります。
まとめ:主体性を育むための親の関わり方
子どもの主体性を育む鍵は、子どもに何かを働きかけて促すことではありません。
保護者自身が子どもを信じて見守る心のゆとりを手に入れることです。子どもに何かをしてあげないと、と頑張りすぎなくていいんです。
- 提案や誘導を控えて、見守る
- 失敗も含めて、信じて任せる
- 一緒の時間は「解決」より「楽しむ」ことを大切にする
この関わり方の積み重ねが、子どもの「自分でできる」という感覚を育てます。親の何気ない選択が、子どもの未来を支える大きな力になるのです。
子どもの主体性を尊重した関わり方のヒントを知りたい方へ。
子どもの主体性を尊重して、親子で「整った関係」を築くための魔法の言葉についてお話しています。
→ 今日の心づもりは?──子どもの主体性と親の心の余裕を守る“魔法のことば”
宿題に悩む親子が笑顔になるために、子どもの主体性を尊重した習慣を紹介しています。
この記事を読んでくださり、ありがとうございます。
思春期の子どもを持つ50代母です。
かつて仕事で子育てセミナーを企画運営する中で、専門家の知見や多くの親の悩みに触れてきました。
自身の経験とプロの視点を踏まえ、親の心のゆとりと、子どもの主体性を尊重する姿勢が大切だと確信。
このブログでは、ずぼらな面もあるわたしが、無理せずラクに心地よく暮らすヒント、完璧じゃなくてもいい工夫を発信することで、あなたの子育てを優しく”ととのえる”お手伝いをしたいと考えています。