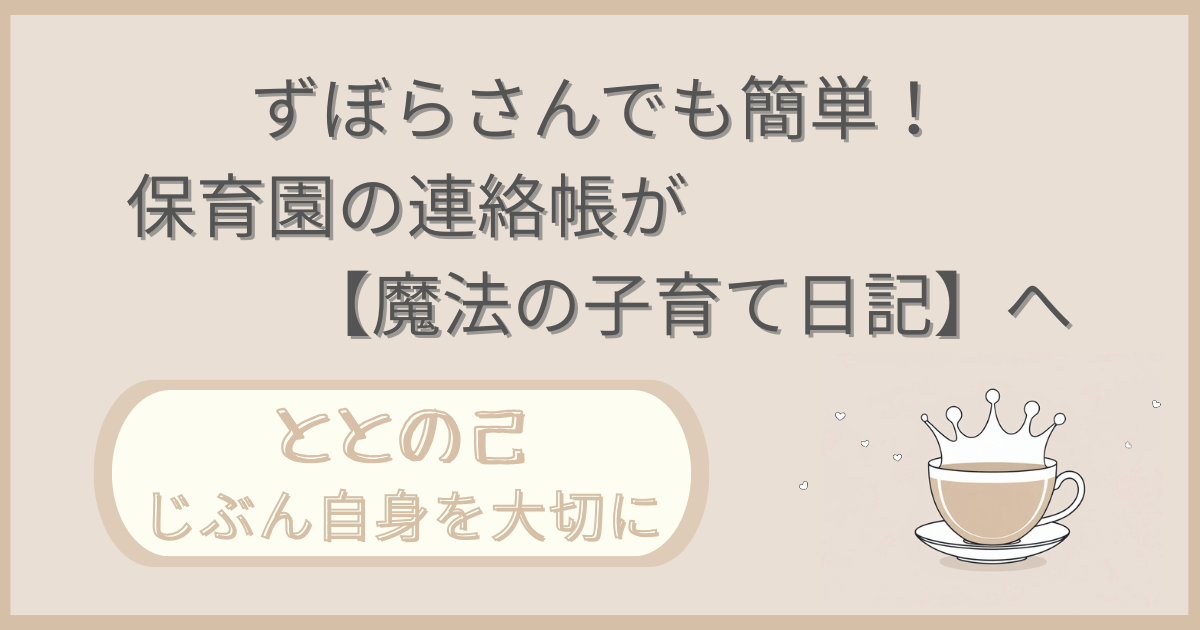子育て日記、つけてみたいけどなかなか続かない。忙しい毎日の中で、新しく何かを始めるのはハードルが高いですよね。
わたしも「めんどくさがりのわたしには無理!」と思っていました。でも、やっと授かった子どもだから、できることはなんでもしてあげたい。そんな思いから、保育園の連絡帳を子育て日記にするという、ずぼらなりのアイデアを思いつきました。
これが、想像以上に子育てを楽しく、豊かなものにしてくれたんです。
良い面だけ書くーー『魔法の子育て日記』」を続けた理由
子育て日記は、嬉しいことも辛いことも正直に書くことで、心の整理につながると言われています。でもわたしは、将来子どもと一緒に読み返すことを前提に、あえて「いいこと」だけを書くことにしました。
これはまるで、『小公女セーラ』がしていた「いいこと探し」のようなもの。物語の中で小公女セーラは、どんなにつらい状況でも、必ずどこかにいいことや美しいものがあると自分に言い聞かせ、それらを「魔法」と呼んでいました。
わたしも同じように子育て中に毎日「魔法」 をみつけて、それを将来の子どもへのメッセージ、わたしが子どもを愛している確かな「愛のあかし」にしたいと思ったのです。
未来の子どもへ届ける愛のメッセージ:魔法の子育て日記
子どもが思春期などに親子関係がうまくいかず心ない言葉をぶつけあったときに、言葉では耳を通り過ぎてしまうようなときに「愛のメッセージ」としてこの日記を渡したいと思ったのです。もしそのとき子どもが自分の存在価値に悩んでいたら、母親が子育てで大変だったことを知って、余計なマイナス感情を抱いてしまうかもしれない、と考えました。だからこそ、連絡帳には、その日あった子どもの良い面だけを書くことにしたのです。といっても、「いちごをうれしそうに食べていた」「帰り道にドングリを拾って楽しんでいた」「池の鯉に興味を持ってずっと観察していた」など、今日あったこと日記だったのですが…。でも、いいことだと思って書いていると、単なる「できこと」が「うれしいこと」に変わってきました。
どんな毎日にも、かならずいいこと「魔法」があるーー子育て中にみつけた「魔法」 をつづる「小公女セーラ風魔法の子育て日記」です。
魔法の子育て日記がもたらした3つのメリット
- 先生が「魔法」を返してくれる
- 「連絡帳を大好きの気持ちでいっぱいにしたい」と先生に伝えておいたら、先生からも子どもの良いところがたくさん返ってくるようになりました。「今日はお友だちとこんな素敵な笑顔でしたよ」「お友だちとこんな遊びをしていました」といった、園での嬉しい情報をもらえるのは、本当に幸せでした。
- 読み返すたびにわたし自身が幸せになれる
- ネガティブな内容を書かなかったことで、読み返すたびに温かい気持ちになります。子どもにこの日記を見せる機会はまだ来ていませんが、イライラしてしまったときでも、この日記を開けば、いかに子どもが愛おしい存在かを再認識でき、心を落ち着かせることができました。
- 日常で「魔法の瞬間」を探すようになる
- プラスの出来事を探す習慣がついたことで、自然と子どもの良い面に目がいくようになりました。腹が立つような出来事も、視点を変えれば面白く感じられることもあります。この習慣は、子育てのストレスを大きく減らしてくれました。
まとめ:連絡帳を「小公女セーラ風魔法の子育て日記」にしてみませんか?
小学校に入り、学年が進んで連絡帳の親記入欄がなくなってからは、わたしも日記を書かなくなってしまいました。
でも、この日記は毎日完璧につけたわけではありません。疲れて子どもにいいところに目を向けられない日や、忙しい日は必要事項だけを記入したこともあったし、夫に記入をお願いした日も多かったです。それでも、この連絡帳を育児日記にするというアイデアは、今でも「我ながらいい発想だったな」と自画自賛しています。
わたしと似たようなずぼらさんにこそ、この方法を試してほしいです。ぜひ、いいことだけを記録する「小公女セーラ風魔法の子育て日記」を始めてみませんか。子育ての毎日はあっという間に過ぎていきます。連絡帳を活用したら大切な瞬間を楽しく簡単に記録できます。
わたしは、この日記のおかげで、今とても幸せです。
あわせて読みたい子育てのヒント
子どもの好奇心を引き出し、将来の学びにつながる本当に夢中になるおもちゃ選びのヒント
→知育玩具だけじゃない!わが子の好奇心を引き出すおもちゃ選びのヒント
忙しいママが自分と子どもの「楽しい」を見つけるためのアイディア「ながら遊び」を紹介
→「こなす育児」から卒業!忙しい毎日を笑顔に変える魔法の遊び「ながら遊び」
子どもの主体性を尊重して、親子で「整った関係」を築くための魔法の言葉の説明
→ 今日の心づもりは?──子どもの主体性と親の心の余裕を守る“魔法のことば”
「先に宿題!」ではなく心理学的に正しい声かけで子どもの主体性を育む方法を紹介
→「先に宿題!」がNGなワケ。子どもの主体性が育つ魔法の習慣
入学前からの家庭教師のメリット:勉強嫌いを防ぐ効果、保護者の負担軽減、子どもの好奇心を引き出すを紹介
→幼児期から家庭教師は早い?―「英才教育」ではなく「人生の羅針盤」
この記事を読んでくださり、ありがとうございます。
思春期の子どもを持つ50代母です。
かつて仕事で子育てセミナーを企画運営する中で、専門家の知見や多くの親の悩みに触れてきました。
自身の経験とプロの視点を踏まえ、親の心のゆとりと、子どもの主体性を尊重する姿勢が大切だと確信。
このブログでは、ずぼらな面もあるわたしが、無理せずラクに心地よく暮らすヒント、完璧じゃなくてもいい工夫を発信することで、あなたの子育てを優しく”ととのえる”お手伝いをしたいと考えています。