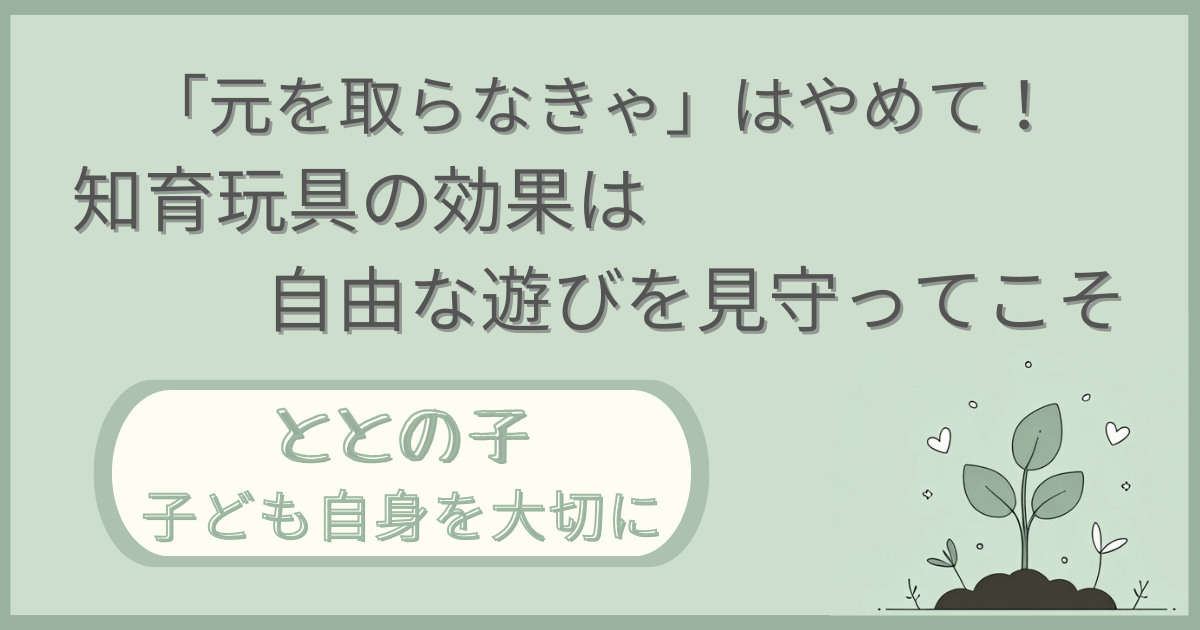子育て中の皆さん、こんな経験はありませんか?
「子どもの知育のために」と奮発して買った、木のおもちゃや知育玩具。でも、子どもは全然興味を示さない……。
わが家もそうでした。ありがたいことに、友人からたくさんの知育玩具や木のおもちゃの「おさがり」を譲り受けました。どれも高価なものばかりで、わが子も喜んでくれるだろうと期待に胸を膨らませていました。
でも、実際には、子どもが熱中しておもちゃで遊ぶ時間はそれほど多くありませんでした。
高価な知育玩具が「最高の学び」にならない時
うちの子は、いわゆる「おもちゃで遊ぶのが好き」なタイプではなかったのかもしれません。
- 平日は保育園で過ごす時間が長かった
- 家ではおもちゃよりも絵本が好きだった
- ぬいぐるみや、母親とのごっこ遊びに夢中だった
さまざまな理由があると思います。でも、全く遊ばなかったわけではありません。数ヶ月に一度、思い出したように木のおもちゃを手に取り、その時は驚くほど集中して遊んでいました。その姿を見て気づいたんです。
子どもは、その時の気分で「遊びたいもの」を選んでいる。そして、本当に興味を持った時こそ、遊びは「最高の学び」になるのだと。
「元を取らなきゃ」の呪縛を解くカギは「心のゆとり」
もし、わたし自身がおもちゃを購入していたら、きっと「元を取らなくちゃ!」と躍起になっていただろうなって思います。「せっかく買ったんだから、遊んで!」と、子どもの気持ちを無視して、大人の都合を押し付けていたかもしれません。
親が知育玩具で遊んでほしいとこだわると、遊びはもはや子どものためのものではなくなってしまいます。遊びは、子どもが「楽しい!」と感じて自ら取り組むからこそ、知的好奇心や創造性を育む効果が生まれるのです。
幸い、わたしは友人に譲ってもらったおもちゃだったからか、子どもが使っていない間も穏やかな気持ちでいられました。子どもが「遊びたい!」と思った時にだけ、思う存分遊ばせてあげることができたのです。
おもちゃサブスクサービスが「おさがり」の進化版かもしれない理由
わたしが経験した「おさがり」の良さは、親の心の余裕を生み、子どもの主体的な遊びを促してくれました。でも、すべてのおもちゃを「おさがり」でまかなうのは難しいですよね。
そんなときにぜひ検討してほしいのが、おもちゃサブスクサービスです。おもちゃサブスクサービスは、まさにわたしが経験した「おさがりの良さ」を、もっと手軽に、より効果的に得られるサービスだと感じます。
おもちゃサブスクサービスがもたらす3つのメリット
- 心理的な負担が少ない
- 高価なおもちゃを購入しないため、子どもが遊ばなくても「もったいない」という気持ちが生まれません。
- 子どもの主体性を尊重できる
- 「元を取る」という意識がないので、子どもが遊びたい時に遊びたいものを自由に選ばせてあげられます。
- 多様なおもちゃと出会える
- 自宅では買わないような、さまざまな種類のおもちゃを気軽に試せます。
「使わなければ交換すればいい」という気軽さから、普段遊ばないようなおもちゃも試すことができます。もしかしたら、子どもの新たな一面や、意外な興味を発見できるかもしれません。
おもちゃサブスクサービスは、「元を取らなきゃ」とがんばってしまわたしのようなタイプの保護者にとって、心を軽くしてくれる心強い味方です。
まとめ:賢いおもちゃの選び方で、親子ともに笑顔に
わたしの経験から言えるのは、高価な知育玩具を「買って与える」ことは、「元を取らねば」と思ってしまうタイプの親には向いていないということです。
おもちゃサブスクサブスクサービスなら、高価なおもちゃを買い切りではなく、月額でレンタルできます。
- 「全然遊んでくれないな……」→ 次の交換時期に、さっと違うおもちゃに変更できます。
- 「このタイプのおもちゃ、好きかな?」→ 買う前に、試しにレンタルできます。
こうすれば、子どもの「今」の興味に合わせたおもちゃを、常に家に揃えてあげられます。子どもの気持ちを尊重し、心の底から楽しめる遊びを見守ってあげること。それが、子どもの成長にとって一番大切なことだと、わたし自身の経験から強く感じています。
「元を取らなきゃ!」という呪縛から解放され、子どもも親も笑顔でいられるおもちゃサブスクサービス。子どもの主体性と創造性を育むために、一度検討してみてはいかがでしょうか?
主体性を育む子どもの遊びやおもちゃに興味がある方へ。
最安値にこだわらないこだわり別のおもちゃサブスクサービスおすすめ紹介(人気5社の徹底比較表つき)
→記事:【後悔しない】おもちゃサブスクサービスの賢い選び方|最安値にこだわらない価値とは?
子どもの好奇心を引き出し、将来の学びにつながる本当に夢中になるおもちゃ選びのヒント
→記事:知育玩具だけじゃない!わが子の好奇心を引き出すおもちゃ選びのヒント
忙しいママが自分と子どもの「楽しい」を見つけるためのアイディア「ながら遊び」を紹介
→記事:「こなす育児」から卒業!忙しい毎日を笑顔に変える魔法の遊び「ながら遊び」
子どもの主体性を尊重した関わり方のヒントを知りたい方へ。
子どもの主体性を尊重して、親子で「整った関係」を築くための魔法の言葉の説明
→ 記事:今日の心づもりは?──子どもの主体性と親の心の余裕を守る“魔法のことば”
「先に宿題!」ではなく心理学的に正しい声かけで子どもの主体性を育む方法を紹介
→記事:「先に宿題!」がNGなワケ。子どもの主体性が育つ魔法の習慣
この記事を読んでくださり、ありがとうございます。
思春期の子どもを持つ50代母です。
かつて仕事で子育てセミナーを企画運営する中で、専門家の知見や多くの親の悩みに触れてきました。
自身の経験とプロの視点を踏まえ、親の心のゆとりと、子どもの主体性を尊重する姿勢が大切だと確信。
このブログでは、ずぼらな面もあるわたしが、無理せずラクに心地よく暮らすヒント、完璧じゃなくてもいい工夫を発信することで、あなたの子育てを優しく”ととのえる”お手伝いをしたいと考えています。