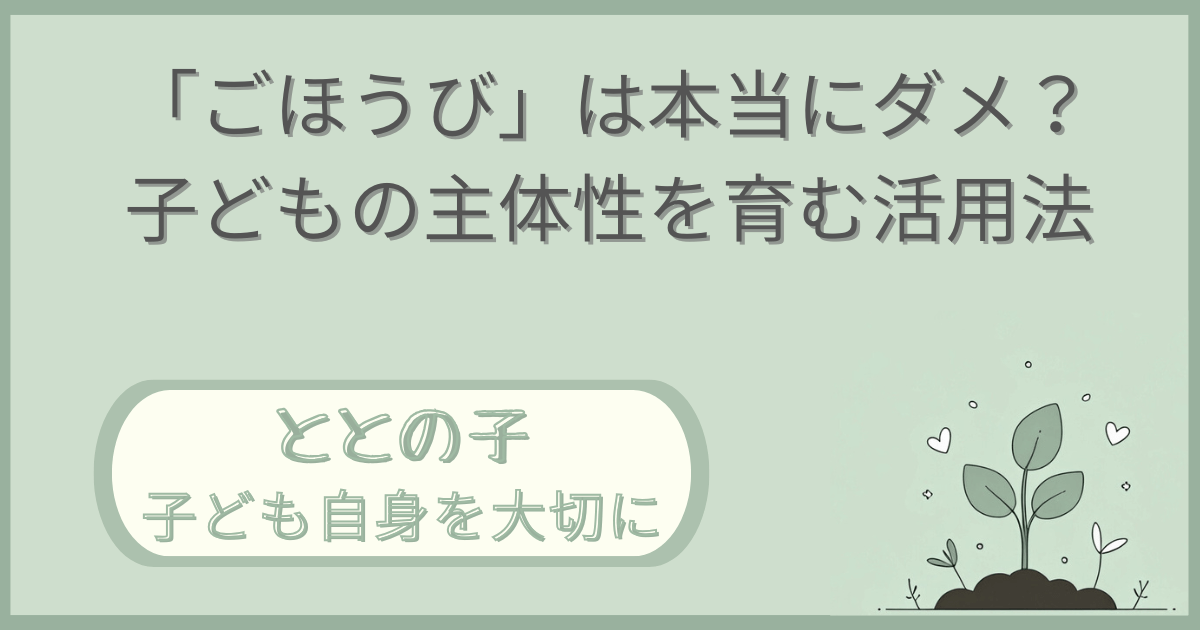最終更新日:2025.09.29
子育てをしていると、「ごほうびで釣るようなことはよくない」という声を耳にすることがあります。でも、頑張っている子どもを見ると、「何かごほうびをあげたい」と思うのは、親として自然な気持ちですよね。この「ごほうび」は、子どものやる気を本当に損ねてしまうのでしょうか?
実は、心理学の動機づけ理論を理解すれば、「ごほうび」は単なる報酬ではなく、子どもの主体性を育むための大切なツール、そして親子の喜びを深める手段として活用できます。
1. 行動の源泉:内発的動機づけと外発的動機づけの「質」
私たちの行動の動機には、大きく分けて2つの種類があります。
- 外発的動機づけ: 行動の結果得られる報酬や罰が目的となる動機です。
- 内発的動機づけ: 活動そのものが目的となり、それ自体に喜びや面白さを見出す動機です。
外発的な報酬が内発的なモチベーションを低下させることがあるのは事実です。しかし、心理学者デシとライアンが提唱した自己決定理論(Self-Determination Theory)によれば、ごほうびは決して悪者ではありません。鍵となるのは、外発的動機づけの「質」を高め、内発的な動機に「内面化」させることです。
2. 主体性を育む3つの鍵と「喜びの共有」の役割
自己決定理論では、人間が持つ「自律性(自分で決める感覚)」「有能感(自分はできる感覚)」「関係性(誰かと繋がっている感覚)」の3つの基本的な心理的欲求が満たされると、やる気が高まるとされています。
自律性の広がりとしての「ごほうび計画」
ごほうびも含めて子ども自身が計画を立てることは、自律性を育む素晴らしい機会です。
「やりたいこと」ばかりではない学習やお手伝いに対し、お子さん自身が「これをやったら、ごほうびにこれをしよう」と計画を立てる。この主体的な計画の経験こそが、モチベーションを維持するための自分なりの方法を見つけるプロセスであり、将来的な自己調整能力につながります。
ごほうびを自己調整のツールとして活用することで、外発的動機づけの質は高まり、行動が自分の目標と結びついているという感覚が生まれます。
達成の「喜びの共有」が満たす二つの欲求
ごほうびの使い方が失敗するのは、親がごほうびを通じて行動をコントロールしようとする(統制的側面)が強すぎる場合です。成功の鍵は、ごほうびが「努力や目標達成を認めるメッセージ」として機能する(情報的側面)ことです。
①有能感の承認
自律性に基づいて自分で立てた計画が達成されたとき、親がその結果を心から喜ぶことで、子どもは「自分で決めたことをやりきれた」という有能感を強く感じます。親の喜びは、子どもにとって「自分の行動は正しかった」という強力な承認になります。
②関係性の確立
それ以上に大切なのは、「目標達成を一緒に喜ぶ姿勢」が、「関係性」の欲求を満たすことです。
ごほうびを「報酬」として与えるのではなく、「あなたの成功を、私も心から嬉しく思っているよ」と伝えることで、親子の間に情緒的な繋がりや共感が生まれます。これは、「お金を払うからやる」という交換関係ではなく、「わたしが頑張ると、親も喜んでくれる」という安心感につながり、次の主体的行動へのエネルギーとなるのです。
3. 親の関わり方:「ごほうび」を「共感と承認」に変える
頑張っている子どもに「ごほうび」をあげたいという親の気持ちは、無理に否定する必要はありません。この気持ちを、「条件付きの報酬」ではなく、「応援」と「喜びの共有」として表現しましょう。
✕ 事前の「約束」をしない
「○○したら買ってあげる」という条件付きの「ごほうび」は、子どもの行動をコントロールしようとするニュアンス(統制的側面)が強くなります。
○「応援」と「共感」のメッセージを伝える
もし何か物質的なものを与えるとしても、それは「目標達成という素晴らしい出来事を祝う記念品」として位置づけます。大切なのは、以下のメッセージです。
- 努力の承認(プロセス評価):頑張っている姿を見たとき、「熱心に取り組んでるね」「毎日コツコツ続けていてすごいよ」と努力のプロセスを承認します。
- 喜びの共有(目標達成の共感):いい結果が出たとき、「あなたが一生懸命努力して、自分で立てた目標を達成できて、本当に嬉しい!その喜びを分かち合いたくて、これをプレゼントしたくなったよ」という姿勢を伝えましょう。
このように、親が一方的に与えるのではなく、子どもの主体的な活動と達成を心から喜び、「共感と承認」として活用することが、成長を力強くサポートします。「ごほうび=悪いもの」と決めつけるのではなく、その使い方と、親子の文脈を理解することが大切なのです。
子どもの主体性を尊重した関わり方のヒントを知りたい方へ。
子どもの主体性を尊重して、親子で「整った関係」を築くための魔法の言葉についてお話しています。
→ 今日の心づもりは?──子どもの主体性と親の心の余裕を守る“魔法のことば”
子どもの主体性を育むための方法を、親の優しい言葉に隠された意外な落とし穴と親の心のゆとりに焦点を当てて解説しています。
→親の「優しい言葉」が、子どもの主体性を奪っているかもしれない
宿題に悩む親子が笑顔になるために、子どもの主体性を尊重した習慣を紹介しています。
この記事を読んでくださり、ありがとうございます。
思春期の子どもを持つ50代母です。
かつて仕事で子育てセミナーを企画運営する中で、専門家の知見や多くの親の悩みに触れてきました。
自身の経験とプロの視点を踏まえ、親の心のゆとりと、子どもの主体性を尊重する姿勢が大切だと確信。
このブログでは、ずぼらな面もあるわたしが、無理せずラクに心地よく暮らすヒント、完璧じゃなくてもいい工夫を発信することで、あなたの子育てを優しく”ととのえる”お手伝いをしたいと考えています。