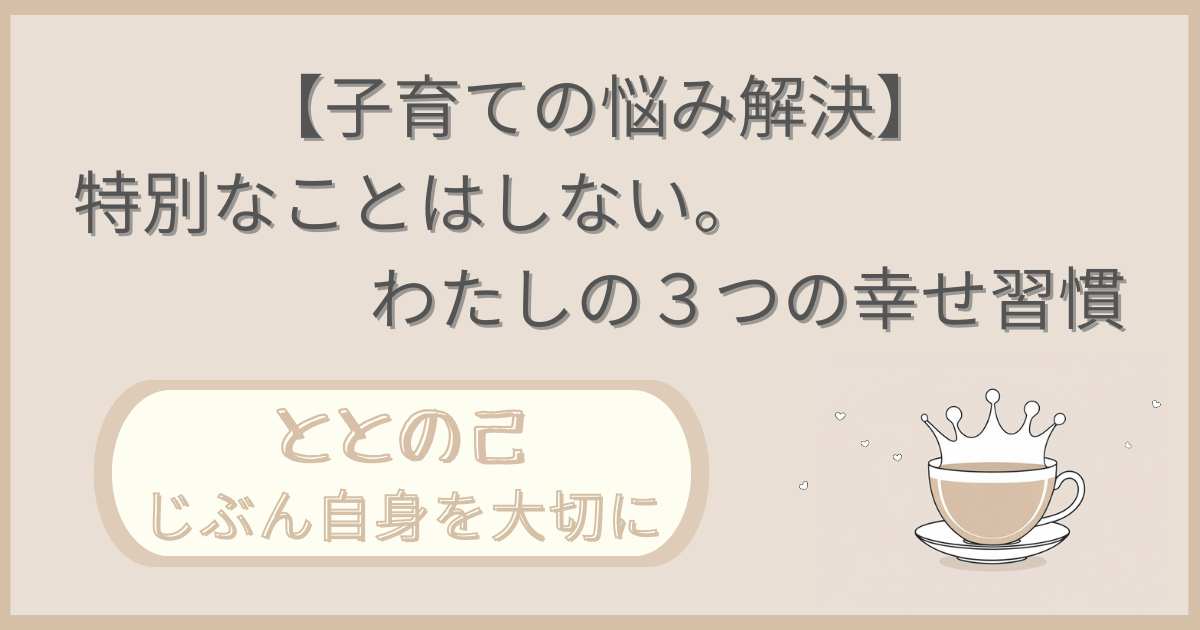ブログのカテゴリー整理から気づいた、わたしの幸せの形
みなさん、こんにちは。
先日、このブログのカテゴリーを整理していて、あることに気づきました。
「毎日を楽しく過ごしている」と自負しているのに、記事を分類してみると、「楽しむ」カテゴリーの記事がほとんどありませんでした。ほとんどの記事が「整える」や「備える」といったカテゴリーに収まってしまうんです。
最初は不思議に思っていたのですが、すぐにその理由が分かりました。
わたしにとって、「整っている日常」こそが、日々を「楽しむ」こととイコールだったのです。
今回は、子育て中のわたしが、毎日を楽しく、そして幸せに過ごすために大切にしている3つの考え方をご紹介します。
1. 子どもの主体性を尊重するスケジューリング術
「遊んでばかりで○○していない」って子どもにイライラしてしまうこと、ありますよね。
わが家では、やることもやる時間もどうするか、スケジュール管理は子どもの主体性に任せています。
わたしは事前に「今日の心づもりは?」と子どもが決めたスケジュールを共有するだけ。自分で決めたスケジュールだから子どもはちゃんと守るようになります。こうすることで、急かしたり、怒ったりすることが減り、お互いに気持ちよく過ごすことができるようになりました。
子どもの主体性を尊重して任せてしまえば、親の心にゆとりがうまれ気持ちよく整った日常を過ごせます。
具体的にどうやっているの? と思った方は、▶今日の心づもりは?──子どもの主体性と親の心の余裕を守る“魔法のことば”を参考にしてみてください。
2. ちょっとした瞬間に伝え合う「好き」という言葉
忙しい毎日の中で、ふと立ち止まる瞬間。そんな時に子どもからもらえる「好き」という言葉は、何よりもわたしの心を温めてくれます。わたしが「好き」を伝えたときの子どものうれしそうな顔は、わたしの心を満たしてくれます。
料理を作っているとき、ただいまと顔を合わせたとき、時にはただぼーっとしている時。特別なことをしていなくても、ふとしたタイミングで伝えあう「好き」という言葉は、幸せを運ぶ心の栄養です。
言葉に詰まったとき、どうやって「好き」を伝えたらいいか悩んだら、▶ 【子育てに疲れたママへ】心が楽になる2つの習慣「褒め言葉の収穫」を参考にしてみてください。
3. おたがいの「個」を尊重する信頼関係
夫婦や親子であっても、それぞれが別の人間。おたがいいの「個」を尊重しあうことは、とても大切なことだと考えています。
たとえば、子どもに入れてもらうコーヒータイム。
子どもがわたしにコーヒーを入れてくれるのは、実は「自分のプライベートスペースを確保」したいから。子どもは一人でリビングでくつろぎたい、作業したいという気持ちがあるんです。わたしはそれを理解して、あえて寝室に引っ込んでいます。
すると、休憩時間になると、子どもがコーヒーとお菓子を運んできてくれます。「ママ、休憩してね」と。
一見すると、わたしがリビングから追い出されているように見えるかもしれません。でも、子どもは「プライベートを尊重してもらっている」と感じています。だから「ありがとう」という気持ちを込めてコーヒーを淹れてくれるのです。
さらに面白いのは、普段はあまりお手伝いをしない子どもでも、わたしが疲れて弱っている時には何も言わなくても自主的に動いてくれること。本人いわく「ママが弱っているとバフ(強化効果)がかかるんだよ」と(笑)。そんな風に自然と助けてくれる姿を見ると、お互いの「個」を尊重しているからこそ生まれる信頼関係なのだと実感します。
人に入れてもらった温かいコーヒーは格別です。そして、「お互いの個を大切にしている」というこの関係性が、整った日常をかたちづくり、日々に喜びをもたらしてくれています。
まとめ:整えることと楽しむことは、つながっている
子育て中は、毎日が慌ただしく、目の前のことを「整える」だけで精一杯になりがちです。でも、実はその「整った日常」こそが、何よりも特別な「楽しい」時間だったりします。
- 子どもの主体性を尊重すること
- 「心の栄養」になる「好き」を伝え合うこと
- お互いの「個」を尊重できること
この3つの考え方が、わたしの毎日を楽しく、そして幸せにしてくれます。
もしあなたが今、少し疲れているなら、無理に何かをしようとしなくても大丈夫。ふと立ち止まり、頑張っている自分をそっとねぎらってあげてください。あなたの心のゆとりが、日常の小さな「ととのう」を、「楽しい」をみつけてくれます。
あなたにとっての「日常の幸せ」はどんなことですか?もしよかったら、コメント欄で教えてください。あなたの幸せのヒントが、誰かの心にも届くかもしれません。
子どもの主体性を尊重した関わり方のヒントを知りたい方へ。
子どもの主体性を尊重して、親子で「整った関係」を築くための魔法の言葉についてお話しています。
→ 今日の心づもりは?──子どもの主体性と親の心の余裕を守る“魔法のことば”
子どもの主体性を育むための方法を、親の優しい言葉に隠された意外な落とし穴と親の心のゆとりに焦点を当てて解説しています。
→親の「優しい言葉」が、子どもの主体性を奪っているかもしれない
宿題に悩む親子が笑顔になるために、子どもの主体性を尊重した習慣を紹介しています。
この記事を読んでくださり、ありがとうございます。
思春期の子どもを持つ50代母です。
かつて仕事で子育てセミナーを企画運営する中で、専門家の知見や多くの親の悩みに触れてきました。
自身の経験とプロの視点を踏まえ、親の心のゆとりと、子どもの主体性を尊重する姿勢が大切だと確信。
このブログでは、ずぼらな面もあるわたしが、無理せずラクに心地よく暮らすヒント、完璧じゃなくてもいい工夫を発信することで、あなたの子育てを優しく”ととのえる”お手伝いをしたいと考えています。